事故を起こしてしまった場合
もし、トラックで走行中に事故を起こしてしまった場合は、
陸運局に対する報告が必要になる場合があります。
え?
警察や救急車を呼んだりしただけではダメなんですか?
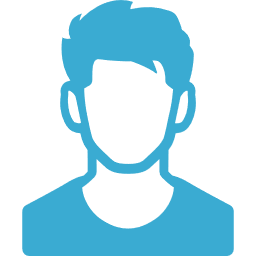

はい、ダメです。
事故を起こしてしまったときは、運輸局などにきちんと報告するというルールがあるのです。
それはどんな事故でも全て報告する必要があるんですか?
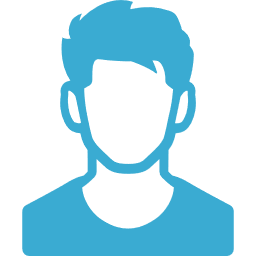

いいえ、報告の対象となる事故は法律できめられています。
なるほど、それはどんな事故ですか?
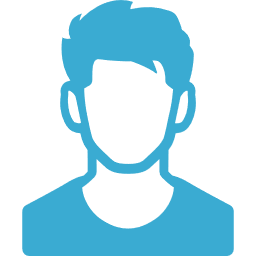

はい、大きく分けて2つに分かれます。
報告が必要な事故その①:速報事故
- 2名以上の死者を出してしまった場合
- 5名以上の重傷者(※1)を出してしまった場合
- 10名以上の負傷者(※2)を出してしまった場合
- 酒気帯び運転を伴う事故の場合
- 危険物(※3)を積んだトラックが転覆、転落、火災を起こして危険物等が全部又は一部飛び散ったり漏れたりした場合や電車と衝突、もしくは接触して危険物等が全部又は一部が飛び散ったり漏れたりした事故
- 国土交通大臣が必要と判断したとき(※4)
これは確かにかなり大きな事故ですね。
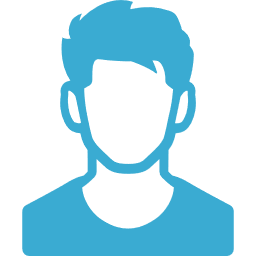

はい、事故の中でも特に重大な事故については“速報”が必要になるのです。
“速報”ということはすぐに報告しなくてはいけないのですか?
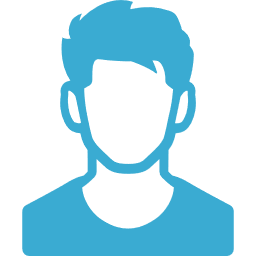

そのとおりです。以下のようにルールが決められています。
速報のルール
- ①事故を起こしてしまってから24時間以内に報告
- ②電話かFAXで報告
- ③連絡先は運輸支局の整備保安担当
“速報”の対象となる事故はわかりました。その他の事故の場合はどうするのですか?
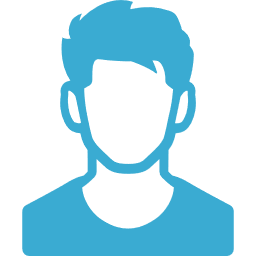

さきほど報告の対象となる事故は大きく分けて2つといいましたね。ここでもう1つを紹介します。
報告が必要な事故その②:事故報告
事故報告とは、以下の項目に該当する事故があった日から30日以内に、
運輸支局に所定の報告書を提出する制度です。
これは、本社が一括して提出するのではなく、
営業所単位で提出します。
なので、提出先は、その営業所を管轄する運輸支局の
整備担当窓口になります。
事故報告書の提出が必要な事故
- トラックが転覆したり転落した場合
- トラックや荷物が火災を起こした場合
- 踏切で電車と衝突や接触した場合
- 10台以上の車の玉突きなどの接触事故を起こした場合
- 死者または重傷者(※1)を出してしまった場合
- 10人以上の負傷者(※2)を出してしまった場合
- 積載した危険物(※3)の全部または一部が飛び散ったり漏れたりした場合
- 積載したコンテナが落下した場合
- 飲酒や酒気帯び、無免許、無資格、薬物乱用、居眠り運転等をした場合
- 運転手の急病、持病などにより途中でトラックの運転が出来なくなった場合
- 救護義務違反があった場合
- トラックの装置等(※5)の故障により走れなくなった場合※6
- 故障や整備不良によりタイヤが外れたりトレーラーが分離してしまった場合※6
- 橋や送電線などの鉄道施設を壊してしまい3時間以上鉄道の運転を休止させた場合
- 高速道路や自動車専用道路で3時間以上の通行を禁止させた場合
- 国土交通大臣が報告が必要だと認めて指示をした場合
言葉の定義
事故報告書が必要な事故はなんとなくイメージ出来たかと思います。
以下は、少し説明が必要な言葉の定義になります。
※1 重傷とは
怪我の度合いで、なんとなく骨折したから重傷、
とかではなくきちんと法律で定義が決められています。
自動車事故損害賠償補償法施行令に
その定義が定められていて、それが以下になります。
(自動車事故損害賠償補償法施行令第5条)
二 次の傷害を受けた者
イ 脊柱の骨折、その骨折によって脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕または前腕の骨折、またその骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿または下腿の骨折
ニ 内臓の破裂、またはその破裂により腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
三 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内蔵の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害
※2 負傷者とは
重傷者と負傷者を足した合計の数です。
※3 危険物とは
・消防法第2条第7項に規定する危険物
・火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
・高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
・原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれにより汚染された物
・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条条第2項に規定する放射性同位元素及びそれにより汚染された物
・シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
・道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に関する可燃物
※4 国土交通大臣が特に必要と認めた場合とは
「社会的影響が大きい事故」
と言われる場合にも速報が必要になります。
テレビや新聞等のニュースとして取り上げられたり、
事故に関して取材を受けた場合などはこれに該当します。
ただし、他の速報事故とは若干異なり、
努力義務として
「速報するように務めなければならない」
と定められています。
※5 装置の故障とは
道路運送車両法第5条に装置の定義が掲載れています。
そして故障したから即報告が必要になるわけではなく、
故障により走れなくなった場合に報告が必要になります。
- 原動機及び動力伝達装置
- 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
- 操縦装置
- 制動装置
- ばねその他の緩衝装置
- 燃料装置及び電気装置
- 車枠及び車体
- 連結装置
- 乗車装置及び物品積載装置
- 前面ガラスその他の窓ガラス
- 消音器その他の騒音防止装置
- ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
- 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
- 警音器その他の警報装置
- 方向指示器その他の指示装置
- 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
- 速度計、走行距離計その他の計器
- 消火器その他の防火装置
- 内圧容器及びその附属装置
- 自動運行装置
- その他政令で定める特に必要な自動車の装置
※6 装置の故障、脱輪、トレーラの分離
この場合は、報告書とは別に定められた事項を記載した
書面、図面、写真などを添付する必要があります。
こ、こ、こんなにたくさん細かく決められているんですね…
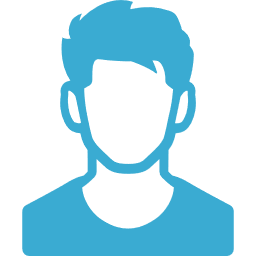

はい、事故については人命にも関わることも多く、原因をしっかりと解明し、
2度と事故を起こさないような体制を整えさせるためにもこのように細かく
ルールが決められています。
なるほど、確かに事故なんて起こしたら大変ですもんね。
きちんと安全運転しなきゃ。
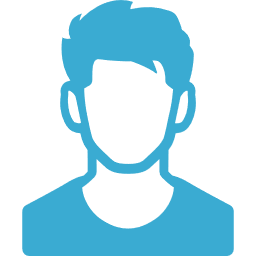

そうですね。安全運転をするにこしたことは有りません。
安全運転は、結局、燃費も安くなるし、事故も減ります。
事故が減ると保険料も安くなります。
燃料代が減ったり保険料が下がったりすれば会社の資金負担が減ります。
そうすれば浮いた費用で給料を多く払ってあげたりできるようになるので
安全運転はメリットしかないんです。
報告対象外の事故の場合
さて、ここまでは陸運局に対する報告について説明しました。
事故を起こしてしまった場合は、
陸運局に対する報告以外にもやるべきことがあります。
え?まだ何かやらなきゃいけないことがあるんですか?
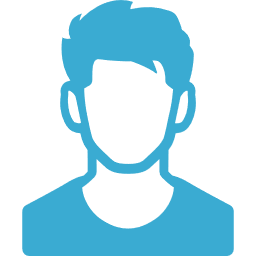

はい、あります。
それは事故記録の作成です。
事故記録簿の作成
事故を起こしてしまった場合、
陸運局への報告書とは別に事故の記録を残さないといけません。
事故の記録を書面に残して、
それを3年間保存すると決められています。
また、事故が発生してから30日以内に
作成することも決められているので、
事故報告を提出したことで安心してしまい、
事故記録を作成するのを忘れてしまわないように注意が必要です。
そして、ここでいう事故とは軽微な事故も含めて事故と言います。
警察を呼んだとか呼ばないとか、
ちょっと擦っただけとかは関係ありません。
必ず事故を起こしたら作成し保存しなければいけないのです。
事故記録を作成する場合に記載する項目は8つです。
- 乗務員の氏名
- 自動車登録番号または識別番号
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の当事者の氏名(運転手ではなく相手がいる場合は相手の名前)
- 損害の程度を含む事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
上記の内容を記載した事故記録をきちんと作成し、
保存しておきましょう。
特に、再発防止策は重要です。
建前の再発防止策ではなく、2度と事故を
起こさないために、原因を調査し、
あらゆる角度から分析し、有効な防止策を考えて、
そして全員が実行して下さい。
